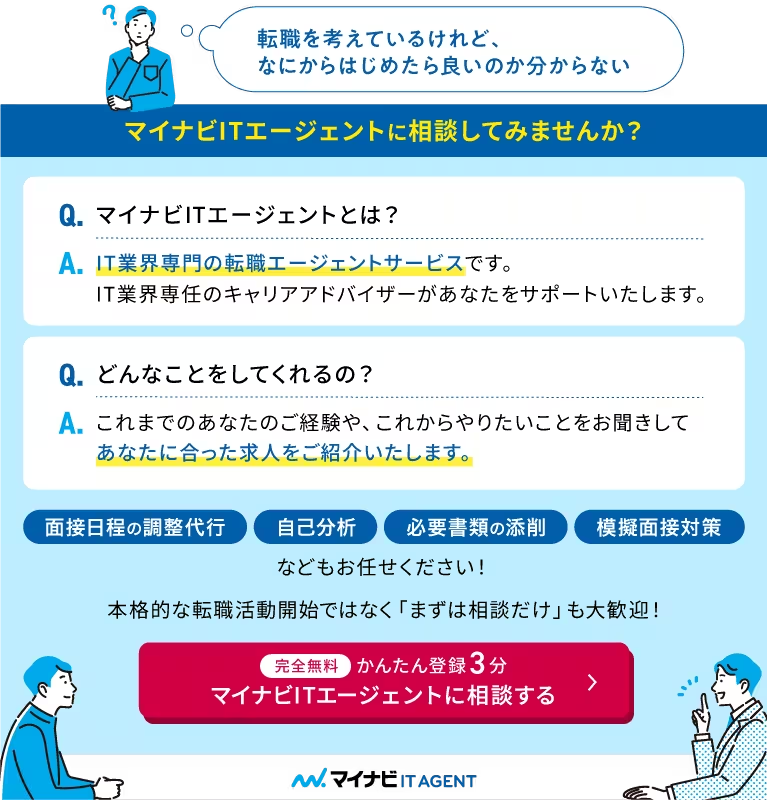企業を変容させる5つのDX技術

蛹が蝶になるような劇的変容(トランスフォーメーション)をビジネスで実現するのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)です。 企業がDXを達成する推進力となるデジタル技術には、代表的なものにAI・ビッグデータ・IoT・ICT・RPAなどがあります。
AI(人工知能)
囲碁ソフトの実力はアマチュア初段クラスと言われてから10年もたたないうちに、囲碁AIはトッププロも太刀打ちできない怪物に育ちました。
ゲームの世界では人間同士が自分の知能で対戦するのがルールですが、ビジネスでは人工知能の力を借りるのは反則でありません。旧式のソフトしか持たない企業と最新のAIを備えた企業では、サービスの質・量・スピード・コストに大きな差が生じます。
とくに、自動車の自動運転を可能にするようなディープラーニングの進化によって、AIのビジネス利用の地平が大きく広がりました。画像認識による製品仕分け・ニーズ予測・マッチング予測・医療診断・デザイン・設計など、その利用範囲は多岐に及びます。
自動翻訳など、そのレベルがまだアマチュア初段クラスのものもありますが、自社のビジネスで適切なシーンにAIを活用することで、企業はトラスフォーメーション(様変わり)する可能性があります。
ビッグデータ
コンピュータの処理能力の飛躍的な向上とAIの技術を組み合わせることで、ビッグデータの利用が可能になりました。
週間天気予報が驚くほど正確で、2~3ヶ月スパンの長期予報もそこそこ当たるのは、ビッグデータを有効利用しているからです。さらに、ビール会社は天候予測を含めたさまざまなビッグデータを用いて、夏のビール需要を予測して生産します。
従来は混沌・カオスでしかなかった膨大な非定型・非構造化データを、volume(量)・velocity(頻度)・variety(多様性)という3つのVを軸に、リアルタイムで構造化し、解釈可能なものにするのがビッグデータ処理技術です。
IoT(モノのインターネット)
家電にマイコンが内蔵されるようになったのは1980年代ですが、そのマイコンがインターネットに接続されたのがIoT(Internet of Things)です。
象印は電気ポットにIoTを装備することで、実家(高齢者世帯)のポットの利用状況から離れて暮らす子どもが親の安否確認ができる「みまもりホットライン」を提供しました。ドローン撮影とインターネットを連結したIoTは、土木工事の測量現場から測量技師の姿を消し去りつつあります。
モノ・センサー・ネットワーク・アプリケーションの4つの要素で構成されるIoTは、「モノ」の用途、操作性を劇的に変え、消費者のライフスタイルをも変える力があります。自社の製品、サービスをIoTの視点から構想し、提供することでDXを実現することが可能です。
ICT(情報・コミュニケーション技術)
コロナ禍でリモートワークやオンライン授業を可能にしたのが、ICT(Information and Communication Technology)です。
SNSが個人のコミュニケーションを様変わりさせたように、ビジネスでもSlack(スラック)・Chatwork(チャットワーク)・Microsoft Teams(マイクロソフトチームズ)などのICTシステムが、企業のコミュニケーションを変容させつつあります。
ソフトウェア開発におけるプロジェクト管理ツールはもちろん、営業活動や建築現場もICTによる変革の波の中にあります。
RPA(ホワイトカラー業務のロボット化)
RPA(Robotic Process Automation)とは、総務・経理・営業管理などのホワイトカラー業務をロボットに代行させるデジタル技術です。もっともRPAが進んでいる業種にコールセンターの自動チャットシステムがあります。
RPAには、定型業務・単純作業をさせるクラス1、データの収集・分析をさせるクラス2、業務プロセスの改善や意思決定までさせるクラス3などのレベルがあります。
クラス3はまだ理念的な段階ですが、人口減少による労働力不足が確実に到来する日本社会ではRPAが企業の命運を握る可能性があります。
企業がDX技術の選択に迷い、意志決定できない理由

DXを駆動するデジタル技術が日々進歩する中で、多くの企業が具体的なDX施策に踏み切れない段階にあります。その理由は「自社にとってのDX」を構想する人材を欠き、実施体制を作れないことにあります。
中堅企業の7割以上が「検討中」または「検討の予定」
「2025年の崖」で経済産業省に尻をたたかれるまでもなく、企業はDXをできるだけ早く推進したいと思っています。(2025年の崖 : 経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で使用された言葉、あらゆる企業は2025年までDXを達成しないと、国際競争力を失って失墜するとされる)
しかし、大企業を除く多くの企業が、DXに一歩も踏み出せない状態にあります。(財)日本能率協会の2020年の調査によると、従業員300人以上3000人未満の中堅企業でも「DXを推進中」は24.8%で、「取り組みを検討中」と「これから検討する予定」が70%以上もあります。従業員300人未満の中小企業にいたっては「DXを推進中」は15.2%にすぎません。
何をするのが自社にとってのDXなのかが分らない
AIやIoTなどのDX技術そのものは専門家の手を借りれば導入・利用することが可能ですが、どんな技術が自社のDXを可能にするのかは、外部の専門家に聞くだけでは分りません。
企業に不足しているのはDX技術そのものよりも、技術とビジネスの結びつきを構想する人材です。成功したスタートアップ企業のように経営トップがそのような人材ならベストですが、一般企業では望めません。
トップではなくても、内部に自社ビジネスとDX技術に詳しい人材がいて、その人を中心にDX推進体制を組織することが「これから検討を予定している」状態を抜け出すためにぜひ必要です。
中小、中堅企業がDXに踏み出せない理由として、レガシーシステムからの移行などにともなう巨額の予算が足かせになっていることが挙げられていますが、その前にデジタルによってトランスフォーメーションした自社のビジネスモデルを描けないことが根本的な問題と言えます。
DXに向けた企業の選択とは「技術の採用」ではなくUX(顧客体験)志向への転換

DXを「どのようなデジタル技術を採用するか」の課題と捉えると、いつまでたっても「検討中」の看板を外すことはできません。
業務を効率化するテクノロジー、生産コストを下げるテクノロジーという発想から、優れた顧客体験(ユーザーエクスペリエンス)を実現するテクノロジーという発想に転換することが必要です。
DXに向けた経営戦略はUX志向から生まれる
DXには明確な経営戦略が欠かせないと言われますが、経営戦略の基礎になるのは優れたUXの実現を志向する経営マインドであり組織文化です。
DXに成功した企業の事例を参考にするときは、成功企業がどのデジタル技術を採用したかではなく、顧客に受け入れられるどのようなUXを提供したか、そのニーズをいかに発見あるいは発明したかということに注目すべきでしょう。
スマホと家電の連携から生まれるニーズ、所有からシェアリングへの価値観の変化から生まれるニーズなど、自社の製品、サービスを「新しいUXの創造」という観点から見直すことが必要です。自社にトランスフォーメーションを起こすのは、顧客体験にトランスフォーメンションを起こすような製品やサービスなのです。
ITエンジニアがDX人材として活躍するために必要なこと

「2025年の崖」を目前にした企業の多くがIT人材の不足を嘆いていますが、企業が求めるDX人材とは、プログラマーやSEなどのIТエンジニアではありません。
もちろんシステム開発にプログラマーやSEは欠かせませんが、いま企業が求めているのは、ビジネスとIТ技術の結びつきを構想し、主導するDXプロデューサーです。
若いエンジニアがキャリアの先にDXプロデューサーを目指すとしたら、まずAIエンジニアやビッグデータサイエンティスト、データサイエンティストなどを目指す道が考えられます。しかし、それが終着点ではなく、顧客・ビジネス・業界環境についての深い理解と、組織をけん引するマネジメント力、利害関係者を調整する交渉力を身につけなくてはなりません。
これは将来的な課題というより、現在行っている業務の中で意識して養っていきたい能力です。プロジェクトの要件定義の中にもビジネスを理解するヒントがあり、チーム運営の中にもマネジメント力や交渉力を身につける機会があります。このような機会を通じて、広い意味でのビジネスパーソンとしての能力、力量を養っていきましょう。
編集部オススメコンテンツ
アンドエンジニアへの取材依頼、情報提供などはこちらから