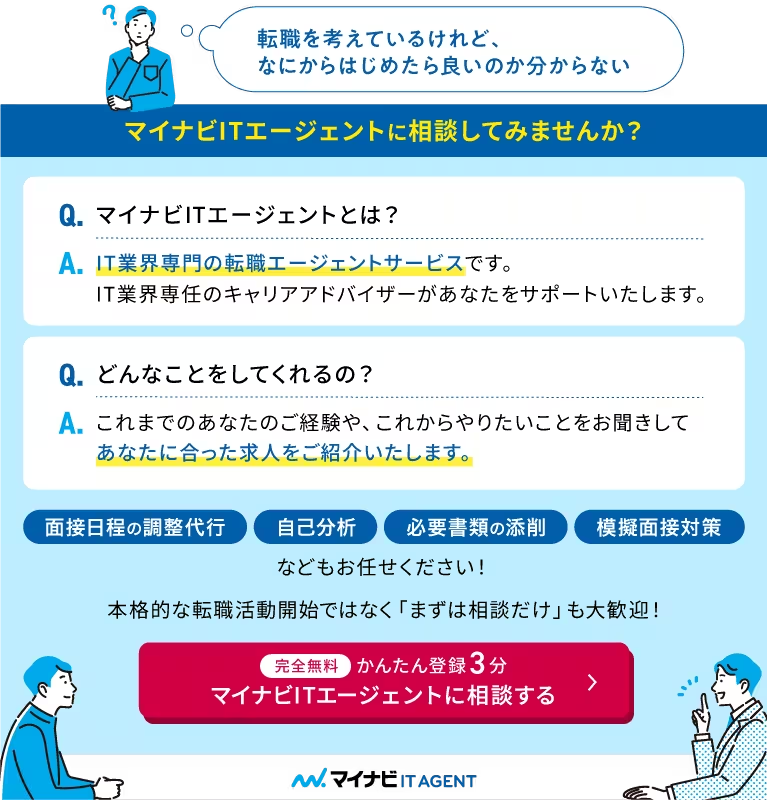近年、活況を帯びる「X-Tech(クロステック)」。アンドエンジニアでは『話題のX-Techに迫る』と題し、さまざまな産業界でテクノロジーを用いて課題解決に挑む方々に、その戦略や実現したい世界観についてインタビューを行います。第1弾は、医療×テクノロジー。自身も医師免許を持ちながら、行政や民間企業での活躍を経てメドテック分野でのスタートアップ企業を立ち上げた、ヘッジホッグ・メドテック社のCEO川田 裕美氏にお話を伺いました。
川田 裕美氏 プロフィール
医師、医学博士、産業医。 2014年に厚生労働省入省。 2017年に株式会社メドレーに参画し、オンライン診療に関して、Government Relations、アカデミアとの連携を推進。2020年からソフトバンク株式会社にて、DTx領域の投資検討及び海外企業とのJV設立を担当。2021年、株式会社ヘッジホッグ・メドテック設立。
異色の経歴を経て、メドテックベンチャーの立ち上げへ


川田さんは医師でありながら、厚生労働省で官僚を務められたり、民間企業でJV設立を支援されたりと、とてもユニークなご経歴をお持ちと伺いました。

はい。学生時代から公衆衛生学に興味がありました。 研修医として2年間病院で働いたあと、興味があった予防領域に挑戦したいと思い、厚生労働省に医系技官として入省しました。患者さんが重症化する手前の状態にアプローチしたいと考えたとき、病院の外で働いたほうが多面的な取り組みができるのではないかと思ったからです。 入省後は、難病対策や感染症対策を担当する部署に所属し、法律の策定や研究推進などを担当しました。

実際に官僚として働いてみて、どんな印象を持ちましたか?

社会的な影響力の大きさを痛感し、とてもやりがいがありました。 一方で患者さん一人ひとりの顔が見えないため、本当に喜んでもらえているのだろうかという感触を得ることができなかったんです。次第に「ユーザーの声を聞きたい」想いが強くなり、企業への転職を決意しました。

民間のスタートアップに転職してからはどのようなお仕事をされていたのですか?

一社目のメドレー社では、オンライン診療の普及に従事していました。当時はまだ一般的にオンライン診療への信頼感が得られていない状況だったため、安全性・有用性の周知や行政との調整の役割を担っていました。ちょうどコロナの流行があり、オンライン診療に関する規制が緩和され一区切りついたと感じました。 そのあとはソフトバンクに転職し、医療・ヘルスケア企業への投資部門で経験を積みました。

その後なぜ独立という道を選ばれたのでしょうか。

厚生労働省で制度的な事柄を、民間企業で技術的な事柄やビジネス面の感触を習得してきたたなかで、“自分でやってみる”という選択肢もあるのではないかと思ったことがきっかけでした。 「日本の医療に貢献したい」という想いに動かされた部分が大きく、もともと独立志向が強かったというわけではないんですよ。

そうなんですね。起業をされる過程では、どういう点に苦労されましたか。

エンジニアの方をどう集めるか、どう巻き込むかという点に苦労しました。これまでのフィールドが医療だったので、自分が目指しているサービスを開発するにあたり、どのような人たちに協力を仰ぐか、またどういう職場環境づくりをしていくのが望ましいのかを把握することが、最初にぶつかった壁でしたね。
国内初の「頭痛治療用アプリ」の開発をスタート


現在、頭痛治療のための治療用アプリの開発をされているとのことですが、治療用アプリとはどのようなものなのでしょうか。

患者さんの行動パターンをアプリで認識し、医師との連携を通じて症状の改善につなげることを目的としたツールです。 治療用アプリは日本国内でも最近開発が始まったばかりで、現在はCureApp社が開発した「禁煙治療」に関するアプリと、「高血圧症治療」に関するアプリの2種類しか市場に出ていない状況です。私たちが手がけている「頭痛治療用アプリ」は、順調にローンチされれば頭痛に関して国内初のサービスとなる予定です。

なるほど、完全にブルーオーシャンの市場なんですね。なぜいろいろな疾患があるなかで、「頭痛」に着目されたのですか?

当社のサービスでは、頭痛のなかでも「片頭痛」の患者さんをターゲットとしています。片頭痛の患者さんは受診している人に絞っても国内に300万人程度、潜在的には1,000万人程度の患者さんがいると言われています。また片頭痛に関しては20~50代の患者さんがボリュームゾーンのため、アプリを提供したときにスムーズに使ってもらえるのではないかという見通しから、頭痛治療を最初のテーマに選びました。

アプリはどのような活用をイメージされていますか?

アプリのメリットは手軽さです。個々人がアプリを活用し、そのアプリに日常行動や生活習慣などの情報を溜めていく。そして受診の必要性が生じたときに通知がなされ、病院との連携が行われる「医療機器としてのアプリ」に移行していくサービスを目指しています。

先ほどの数値でいうと、700万人の方は片頭痛の症状を自覚していても、病院に行っていないわけですよね。つまり、我慢していたり、本当は受診が必要なのにできていなかったりする。アプリを通して疾患啓発から受診、治療効果の向上まで一貫して行えればと考えています。

医療機器ということは、病院側にも患者がアプリに入力した情報が蓄積されていくわけですよね。

そうですね。最終的に医療機器として承認が取れたあとは、各医療機関の医師が診療の中で、患者さんに導入していく流れとなります。費用についても、患者さんがアプリに課金するというシステムではなく、病院の窓口でお支払いいただく金額のなかにアプリ代が含まれるというイメージです。

いまはどのような開発フェーズなのですか。

現在は医療機器としての承認を取るためのステップとして、治療効果の検討を行っています。年内には探索的な研究を始めて、数年後の医療機器としての承認を目指している状況です。
医療機器としての治療用アプリに期待される効果


受診前からアプリを使って自分自身の健康を管理することができ、仮に症状がひどくなった場合はそのまま医療機関につないでもらえる。とても便利なしくみですね。

病院で働いていた際、診療時間が短く、患者さんの本質的な悩みやその背景を十分ヒアリングできないもどかしさを感じていました。解決するには、「患者さんの日常的な悩みをデジタルで吸い上げ、定量的に蓄積していく必要があるのでは」と思ったのです。

さらに、既存のヘルスケアツールは、患者さん自身の意思で個別に使用するタイプがメイン。医師側が積極的・主体的に活用できるツールは多くありません。医療現場の状況を鑑みると、「医療機器としてお医者さんが処方する」ツールのほうが有効と考え、アプリ開発に踏み切りました。

現在まさに開発の真っ只中という状況かと思いますが、開発面で障壁となっている事柄はありますか?

患者さん個人ではなく、医師と一緒に使っていくということを考えたときに、どうすれば継続的に利用してもらいやすいのか。またアプリ内で完結するツールではなく、通常の診療との組み合わせで活用してもらうためにはどんな仕様で開発すべきかなど、一つひとつの課題を解決しながら取り組んでいる状況ですね。

なるほど。先行するサービスがないからこそ、一から作り上げるプロセスが求められているのですね。医療現場の反応はいかがですか?

現在様々な医療機関の先生方に相談しながら開発をしている最中なのですが、「いいアプリだね」「使ってみたいね」と言っていただくことも多く、手応えを感じています。 医療の世界はDX化が遅れているといわれているものの、みなさん日常生活においてさまざまなデジタルツールに慣れ親しんでいるわけですから、私たちへの期待も大きいようです。

一方でその先の“効果”については、これからさらなる検証が必要な部分であり、効果がきちんと実証されることで医療機器としての必要性を訴えやすくなるのではないかと考えています。

頭痛治療用アプリのリリース後は、他の疾患に関する治療アプリの開発も考えていらっしゃるのですか?

はい。いろいろな疾患に対応できるよう、当社でも複数のパイプラインを手がけていきたいと思っています。
メドテック領域の未来とは


川田さん個人のご見解として、今後のメドテック市場についてはどのようにお考えですか?

業界としてDX化が遅れている一つの背景に、必要があれば患者さんが来てくれるという環境がベースにあることが大きいと思います。医療現場では診察も含めFace to Faceで情報収集を行うことが一般的でしたが、コロナの影響もあり、対面での情報収集に限界が見られるケースも増えてきています。診療行為において必要な情報をいかにきちんと収集できるかということが、今後さらに重視されるでしょう。

対面での対話、診察が基本にありますが、それ以外の情報を得ようとしたときに、アプリやウェアラブル機器、センサーなどとの組み合わせが重要になってくると思います。さらに収集した情報を自動的に判断するアルゴリズムの開発も求められる。「情報収集」「診断」「治療」の各フェーズで質の高い医療を届け、また医師たちの負担を減らすという点でも、メドテックの必要性はさらに高まると考えています。

そのような市場感も踏まえ、川田さんが今後取り組んでいきたい事柄について教えてください。

「生活と医療の連携」が私自身のテーマだと考えています。治療用アプリを起点に、治療だけでなく、その手前にある個々人の課題や悩みごとを可視化して、必要な方たちを医療につなぐということを実現できるとよいですね。

ちなみにメドテック分野では、どういう人材が求められていると思われますか。

医療的な知識はほとんど必要ないと考えています。一方で、医療現場でどういう人たちがどんな動きをしていて、システムの権限をどのように付与すべきかなど、開発上必要になる情報を楽しく収集できる方が向いていると思います。

私自身もエンジニアと一緒にクリニックへ課題のヒアリングに行ったりすることが多いのですが、自身が知らない分野の人ともコミュニケーションを楽しめる方にはやりがいが大きいのではないでしょうか。私もエンジニアやデザイナーなど、さまざまな方たちとコミュニケーションが取れる職場に身を置くことでたくさん刺激をもらっていますし、新たな価値を生み出す原動力にもなっています。
<取材後記>
ゼロからのスタートにはさまざまな困難や障壁がつきものですが、これまで築いてこられた礎をもとに、明確な目的と目標をもって着実に突き進む川田さんの姿勢からは、並々ならぬ信念と医療に対する情熱を感じました。世の中の医療がもっと便利に、もっと身近に――近い将来、そんな川田さんの想いが結実する日が訪れることでしょう。
ライター

編集部オススメコンテンツ
アンドエンジニアへの取材依頼、情報提供などはこちらから